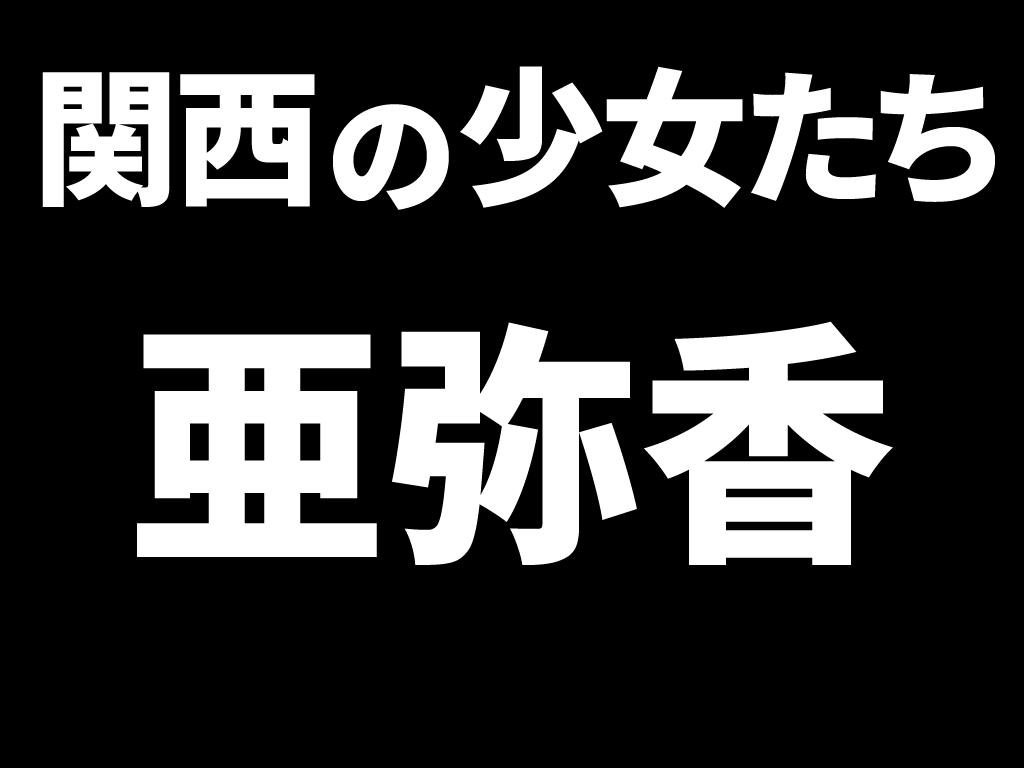
亜弥香
第一章:亜弥香
中学三年生の亜弥香は、関西にある有名歌劇団に進学することを夢見ていた。
そのへんのアイドルのオーディションと違い、歌劇団の入学試験は厳しいものだった。
容姿だけでなく、歌やダンス、学業成績。
そして歌劇団のジェンヌにふさわしい普段の素行も問われた。
亜弥香は子どもの頃からバレエを習い、塾にも通っていて成績は常に上位だった。
そんな彼女には彼氏がいた。
名前はジュンヤ。
野球部のエース。
二人は学校でも有名なカップルだった
野球部の部活で遅くなるジュンヤといっしょに帰るため、いつも亜弥香は放課後図書室で勉強していた。
亜弥香にとって、放課後ジュンヤと一緒に帰宅することが最高の楽しみだった。
歌劇団に入ることを夢見て日々努力を重ねる亜弥香を、ジュンヤは励ましてくれていた。
亜弥香は、教室の一番後ろの席に座りながら、アツコの大きな声が響き渡るのを聞いていた。
表面上、亜弥香とアツコは仲が良いクラスメートだった。
アツコは、クラスの女子たちをまとめるリーダー的存在であり、誰もが彼女に従わざるを得なかった。
彼女の言動に反抗することは、即座に「カーストの下層」に転落することを意味していたからだ。
でも必要以上に仲良くすることもない。
上手に距離をとりながら付き合っていけばいい。
亜弥香はずっとそうしてきた。
ある日の放課後、亜弥香が図書室で勉強しているとアツコが近づいてきた。
「亜弥香、ちょっと話があるんだけど」
アツコは亜弥香の隣にすわって小声で問いかけたきた。
「ねえ、亜弥香。あんた最近パパ活してるって噂聞いたんやけど、本当なの?」
アツコはニヤニヤと笑っていた。
もちろん、そんなことはしていないし、するはずがない。
亜弥香は何を言ってるのと言わんばかりに
「そんなことしてないよ。するわけないやん」
と少し語気を強め、きっぱりと否定した。
「ふーん、そうなんや。でももし興味があったら私に言って。いいパパ知ってるから紹介してあげる。たんまり稼げるよ」
アツコは意味深な笑みを浮かべた。
「パパ活してるのはあなたの方でしょ」
そう言いかけたが、亜弥香は言葉を飲み込んだ。
亜弥香はアツコが何を企んでいるのかを理解した。
表向きは仲良しの誘いのように見えるが、彼女を自分の「子分」に引き込もうとしているのだ。
「ありがとう。でもそういうのは興味ないわ」
亜弥香は優等生らしい笑顔を作りながら、アツコの誘いを断った。
アツコは少し眉をひそめたが
「まぁ、あんたの自由やしな」
と軽く流した。
第二章:タカシとアツコ
放課後、アツコはタカシと待ち合わせしていた。
タカシは40代の男で、パパ活ビデオのプロデューサーをしている。
少女たちをビデオに出演させて金を稼ぐのが仕事だった。
タカシは、アツコの中学の近くにあるファミレスで、いつものようにスマホをいじりながら待っていた。
「アッちゃん、この前の子よかったよ、幸恵ちゃんだっけ。
勝気で生意気なところがお客さんたちにウケてね。
処女ってところも最高やったわ。
で、次はどんな子を紹介してくれるんや?」
アツコはスマホを取り出し、タカシに見せた。
「この子なんかどうやろ?
亜弥香いうて、学年一の美少女で人気モンやねん」
タカシはスマホを覗き込んだ。
「これは美人やなあ。この子ええわ、ぜひ紹介して」
「うん、でもちょっと待って。
まだいま説得してるところやねん。
まあすぐに落ちると思ってるけどな。
あ、そうそう、この子も処女やで(笑)」
「さすがアッちゃん。この子が出てくれたら、きっとまたビデオ売れるやろうなあ」
「あ、そうそう、処女の料金、ギャラに上乗せしておいてや」
「アッちゃんにはかなわんなあ。わかってるって(笑)」
第三章:孤立
「亜弥香、パパ活してるって聞いたけどほんと?」
翌日、今度はさおりが聞いてきた。
亜弥香の心臓がドキっとなった。
さおりまでそんな話を……
噂というのは恐ろしいもので、真実かどうかに関係なく広まってしまう。
「してない、してないよ!」
即座に否定した。
「一体誰がそんなことを言ってたの?」
「え、いや、みんながそう言ってて……。この噂広まってるよ」
「ちがうちがう」
亜弥香の顔は笑っていたが、心の中では不安が渦巻いていた。
噂話がどんどん広がり、クラスメートたちの視線が冷たくなっていくのを感じた。
しかしジュンヤだけは亜弥香を信じていた。
「だれがそんなデタラメを言いふらしてるんだ?見つけたらオレがボコボコにしてやる」
頼もしいことを言ってくれた。
「ありがとう、ジュンヤ」
亜弥香は抱きつき、見つめ合っているとジュンヤがキスしてきた。
これが二人のファーストキスだった。
第四章:破局
しかし噂が沈静化する気配は一向になかった。
学年一の美女・亜弥香がパパ活。
学内では十分スキャンダラスな出来事だった。
最初は女子の一部だけだったのが、徐々に広まっていき、今では他のクラスの男子まで知るところになった。
噂を聞きつけた男子の一人が亜弥香に声をかけてきた。
「あのさ、1回3万円でやらせてくれるって聞いたんだけど。金払うからオレと……」
その瞬間、亜弥香は悲鳴を上げ、持っていたカバンでその男子を殴っていた。
噂話はますますエスカレートし、亜弥香は完全に孤立した。
そしてとうとう担任から生活指導室に呼ばれることになった。
容姿だけじゃなく、学業も素行も優等生だった亜弥香が、生活指導室に呼ばれるというのは、それだけで屈辱的なことだった。
「パパ活なんかしてません。あり得ません」
亜弥香は必死に訴えた。
「そうか。じゃあ本当にパパ活なんかしてないんだね」
だが担任教師の目はまだ半信半疑という感じだった。
亜弥香は自分が歌劇団に進む夢が、こんなデタラメな噂で崩れ去るのを恐れていた。
内申書に悪影響が出れば、彼女の将来は閉ざされてしまう。
それよりも辛かったのは、ジュンヤの態度が変わってきたことだった。
最初は噂なんか信じないと言ってくれていたジュンヤだが、少しずつ距離を取るようになっていたのがわかった。
そして最近ではあまり一緒に帰ろうとしなくなってきていた。
この日も一人で帰ろうとしていたジュンヤを、亜弥香は待ち伏せしていたぐらいだった。
それまでなら会話が途切れることなんかなかった二人だったが、この日はどちらも口を開かない状態だった。
そしてようやくジュンヤの方が口を開いた。
「今日親が二人とも遅いんだ。だから、今からオレの家に来ない?」
「うん、いいよ」
落ち込んでる自分を慰めてくれるのかな。亜弥香はそう思った。
部屋に入るとジュンヤはいきなりキスしてきた。
「もう、びっくりした。どうしたの?」
ジュンヤは黙ってそのまま亜弥香をベッドに押し倒した。
「ちょっと待ってよ。どうしたの、ジュンヤ!」
「前から言ってたじゃん、いつか亜弥香とHしたいって」
「それが今なの?今日なの?」
「だめか?」
「私たちまだ中学生よ。それにキスだって、先週初めてしたばかりじゃない。急すぎるわ」
必死に抵抗する亜弥香に、ジュンヤはあきらめて手を緩めた。
「……なあ、パパ活のしてるって噂、オレ信じてなかったけど……でも」
ジュンヤがそう言いかけたが、亜弥香はそれを遮るように
「いいわ。もう別れよ、わたしたち」
「え、なんで?」
「さようなら」
亜弥香はジュンヤに別れを告げた。
第五章:終局
次の日、完全に孤立している亜弥香に、アツコが再び彼女に近づいてきた。
亜弥香ももうわかっていた。
この噂を広めたのが誰なのかを。
「アツコ、あなたね!あなたがこんな噂広めたんでしょ。私に何の恨みがあって……」
「人聞きの悪いこと言わんといて。うちはあんたの味方やで」
「亜弥香、うちが助けてあげるわ。
うちの頼みをひとつだけ聞いてくれたら、それで全部片付けてあげる。約束するで」
「頼みって何?」
「1回だけパパ活ビデオに出てくれたらええねん。
そしたら私が責任持って噂を鎮めてあげる。
実は私の知り合いのパパ活ビデオのプロデューサーさんに、あんたの写真見せたら、えらい気に入ってなあ。
ぜひこの子にビデオに出て欲しい言うたはるねん。
もちろんギャラも払うし、噂も消えたら一石二鳥や」
「一度だけ……これで全部終わるなら…」
亜弥香は涙をこらえながら、アツコの提案を受け入れた。
翌日、家までアツコが迎えにきた。
車に乗せられ、撮影の場所へ行った。
男優が亜弥香に聞いた。
「イマカレシハイマスカ?」
「いてないです」
撮影が終わり、亜弥香は虚ろな目でその場を後にした。
「おつかれ。プロデューサー喜んでいたよ。はい、ギャラ1万5千円」
亜弥香は一瞬躊躇したが、黙って受け取った。
受け取らなかったら、それでまた反抗的と捉えられかねない。
「みんなにちゃんと言っておくよ、亜弥香はパパ活なんかするような子じゃないって」
亜弥香とってその言葉に何の意味もなかった。
歌劇団への進学はもう無理だろう。
亜弥香にとって高い代償だった。
